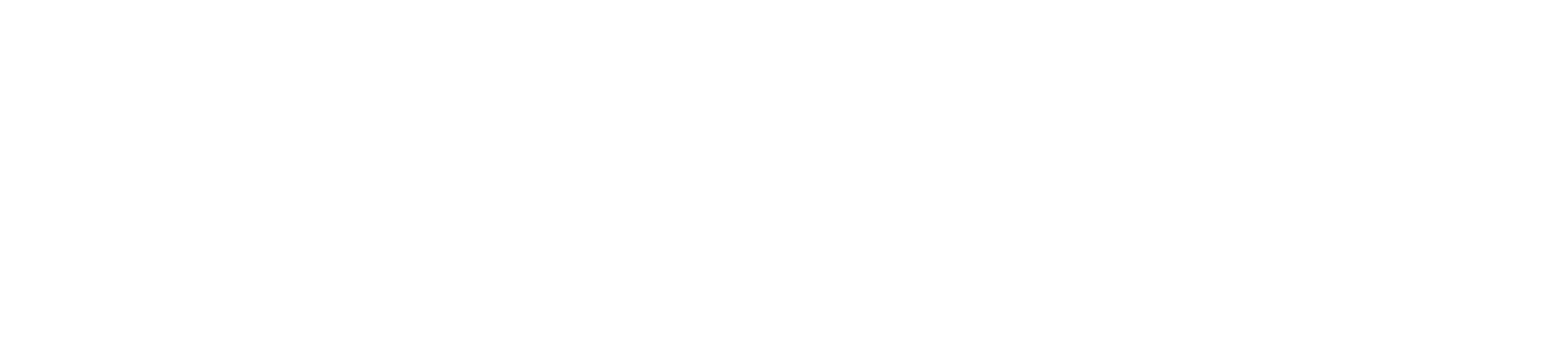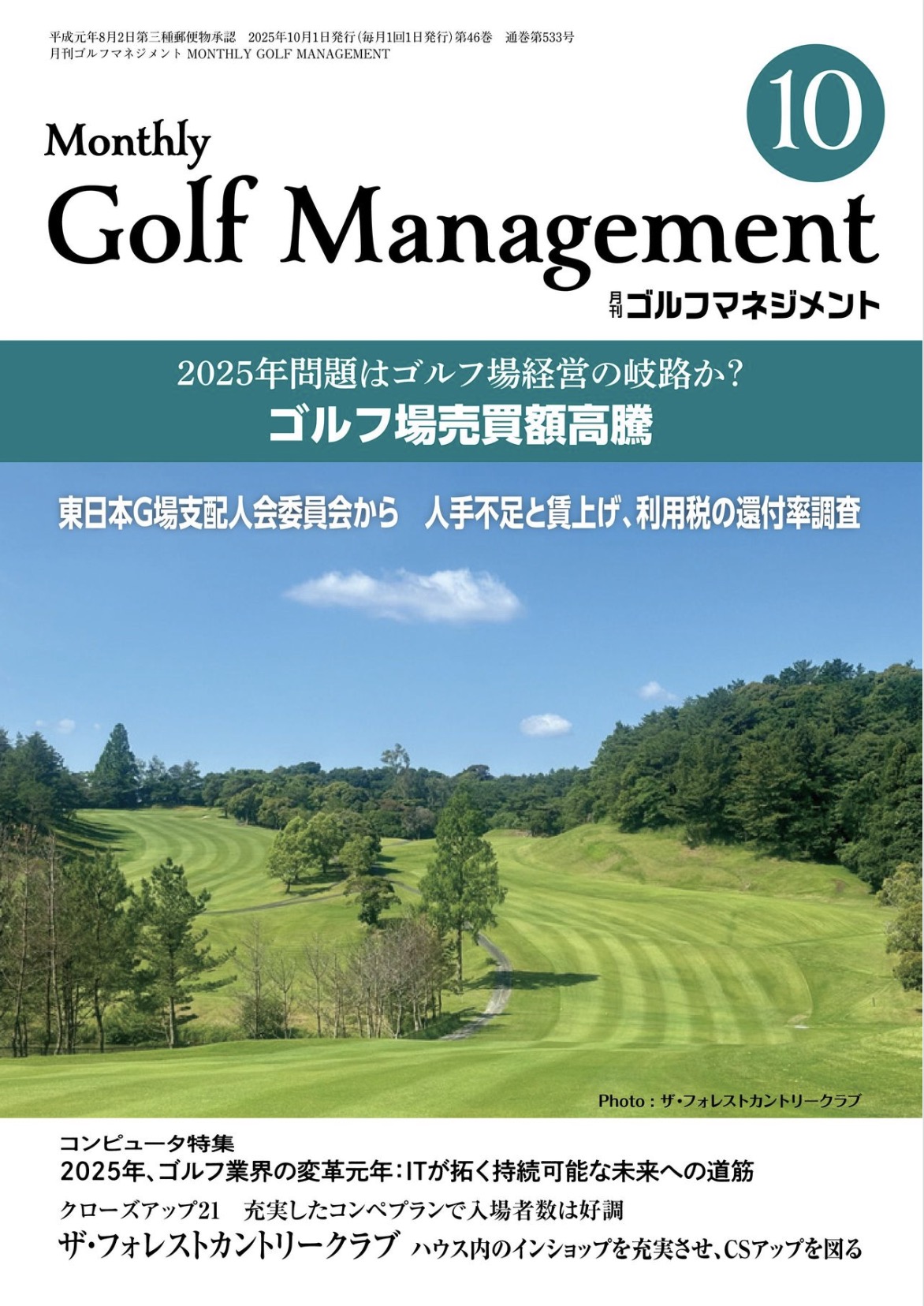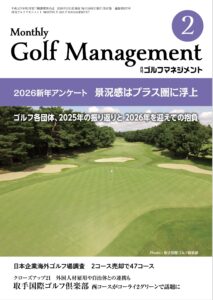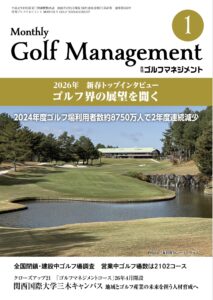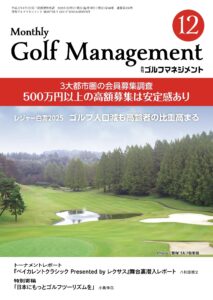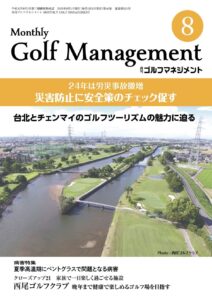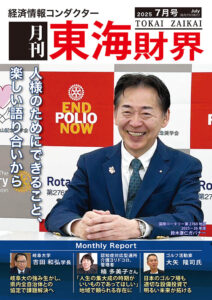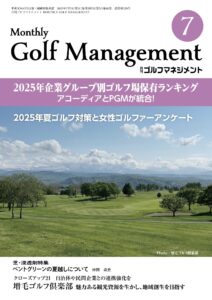ゴルフ界の総合経営誌『月刊ゴルフマネジメント』で、経営に関するコラムを連載させていただいております。
第10回はのテーマは『なぜ企業は間違った判断をするのか?意思決定のセオリーと罠(後編)』です。
月刊ゴルフマネジメントに掲載された記事一覧は下記のリンクからご覧いただけます。
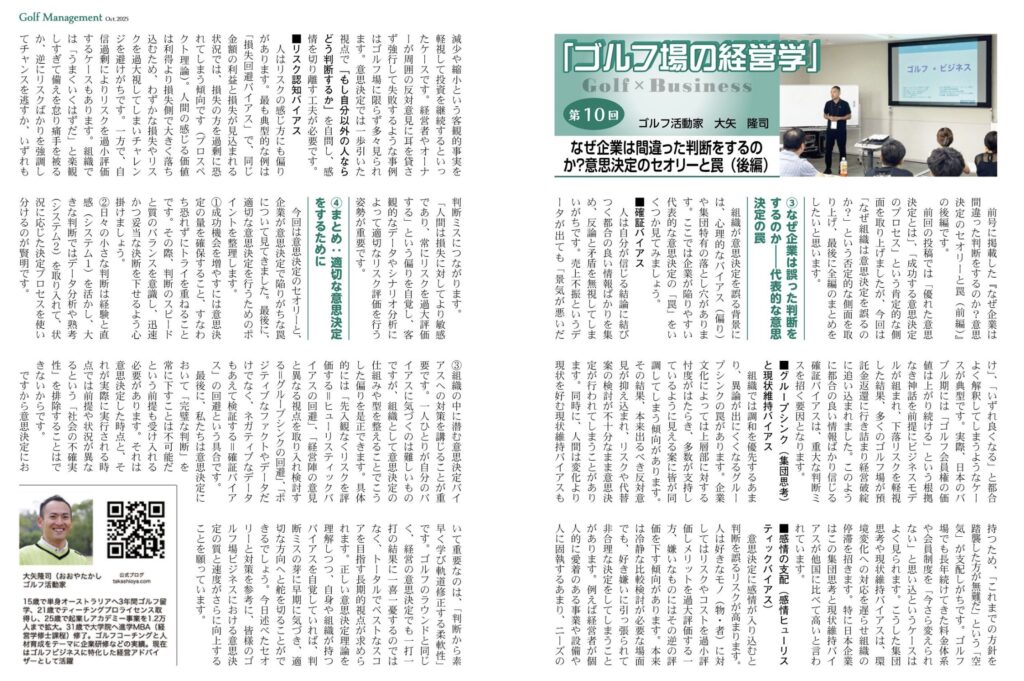
前号に掲載した『なぜ企業は間違った判断をするのか?意思決定のセオリーと罠(前編)』の後編です。
前回の投稿では「優れた意思決定とは」「成功する意思決定のプロセス」という肯定的な側面を取り上げましたが、今回は「なぜ組織は意思決定を誤るのか?」という否定的な側面を取り上げ、最後に全編のまとめをしたいと思います。
3. なぜ企業は誤った判断をするのか――代表的な意思決定の罠
組織が意思決定を誤る背景には、心理的なバイアス(偏り)や集団特有の落とし穴があります。ここでは企業が陥りやすい代表的な意思決定の「罠」をいくつか見てみましょう。
確証バイアス
人は自分が信じる結論に結びつく都合の良い情報ばかりを集め、反論と矛盾を無視してしまいがちです。売上不振というデータが出ても「景気が悪いだけ」「いずれ良くなる」と都合よく解釈してしまうようなケースが典型です。実際、日本のバブル期には「ゴルフ会員権の価値は上がり続ける」という根拠なき神話を前提にビジネスモデルが組まれ、下落リスクを軽視した結果、多くのゴルフ場が預託金返還に行き詰まり経営破綻に追い込まれました。このように都合の良い情報ばかり信じる確証バイアスは、重大な判断ミスを招く要因となります。
グループシンク(集団思考)と現状維持バイアス
組織では調和を優先するあまり、異論が出にくくなるグループシンクの罠があります。企業文化によっては上層部に対する忖度がはたらき、多数が支持しているように見える案に皆が同調してしまう傾向があります。その結果、本来出るべき反対意見が抑え込まれ、リスクや代替案の検討が不十分なまま意思決定が行われてしまうことがあります。同時に、人間は変化より現状を好む現状維持バイアスも持つため、「これまでの方針を踏襲した方が無難だ」という「空気」が支配しがちです。ゴルフ場でも長年続けてきた料金体系や会員制度を「今さら変えられない」と思い込というケースはよく見られます。こうした集団思考や現状維持バイアスは、環境変化への対応を遅らせ組織の停滞を招きます。特に日本企業はこの集団思考と現状維持バイアスが他国に比べて高いと言われています。
感情の支配(感情ヒューリスティックバイアス)
意思決定に感情が入り込むと判断を誤るリスクが高まります。人は好きなモノ(物・者)に対してはリスクやコストを過小評価しメリットを過大評価する一方、嫌いなものにはその逆の評価を下す傾向があります。本来は冷静な比較検討が必要な場面でも、好き嫌いに引っ張られて非合理な決定をしてしまうことがあります。例えば経営者が個人的に愛着のある事業や設備や人に固執するあまり、ニーズの減少や縮小という客観的事実を軽視して投資を継続するといったケースです。経営者やオーナーが周囲の反対意見に耳を貸さず強行して失敗するような事例はゴルフ場に限らず多々見られます。意思決定では一歩引いた視点で「もし自分以外の人ならどう判断するか」を自問し、感情を切り離す工夫が必要です。
リスク認知バイアス
人はリスクの感じ方にも偏りがあります。最も典型的な例は「損失回避バイアス」で、同じ金額の利益と損失が見込まれる状況では、損失の方を過剰に恐れてしまう傾向です(プロスペクト理論)。人間の感じる価値は利得より損失側で大きく落ち込むため、わずかな損失やリスクを過大視してしまいチャレンジを避けがちです。一方で、自信過剰によりリスクを過小評価するケースもあります。組織では「うまくいくはずだ」と楽観しすぎて備えを怠り痛手を被るか、逆にリスクばかりを強調してチャンスを逃すか、いずれも判断ミスにつながります。
「人間は損失に対してより敏感であり、常にリスクを過大評価する」という偏りを自覚し、客観的なデータやシナリオ分析によって適切なリスク評価を行う姿勢が重要です。
4. まとめ:適切な意思決定をするために
今回は意思決定のセオリーと、企業が意思決定で陥りがちな罠について見てきました。最後に、適切な意思決定を行うためのポイントを整理します。
①成功機会を増やすには意思決定の量を確保すること、すなわち恐れずにトライを重ねることです。その際、判断のスピードと質のバランスを意識し、迅速かつ妥当な決断を下せるよう心掛けましょう。
②日々の小さな判断は経験と直感(システム1)を活かし、大きな判断ではデータ分析や熟考(システム2)を取り入れて、状況に応じた決定プロセスを使い分けるのが賢明です。
③組織の中に潜む意思決定バイアスへの対策を講じることが重要です。一人ひとりが自分のバイアスに気づくのは難しいものですが、組織として意思決定の仕組みや型を整えることでこうした偏りを是正できます。具体的には「先入観なくリスクを評価する = ヒューリスティックバイアスの回避」、「経営陣の意見と異なる視点を取り入れ検討する = グループシンクの回避」、「ポジティブなファクトやデータだけでなく、ネガティブなデータもあえて検証する = 確証バイアス」の回避という具合です。
最後に、私たちは意思決定において「完璧な判断」を常に下すことは不可能だという前提も受け入れる必要があります。それは意思決定した時点と、それが実際に実行される時点では前提や状況が異なるという「社会の不確実性」を排除することはできないからです。
ですから意思決定において重要なのは、「判断から素早く学び軌道修正する柔軟性」です。ゴルフのラウンドと同じく、経営の意思決定でも一打一打の結果に一喜一憂するのではなく、トータルでベストなスコアを目指す長期的視点が求められます。正しい意思決定理論を理解しつつ、自身や組織が持つバイアスを自覚していれば、判断ミスの芽に早期に気づき、適切な方向へと舵を切ることができるでしょう。今日述べたセオリーと対策を参考に、皆様のゴルフ場ビジネスにおける意思決定の質と速度がさらに向上することを願っています。