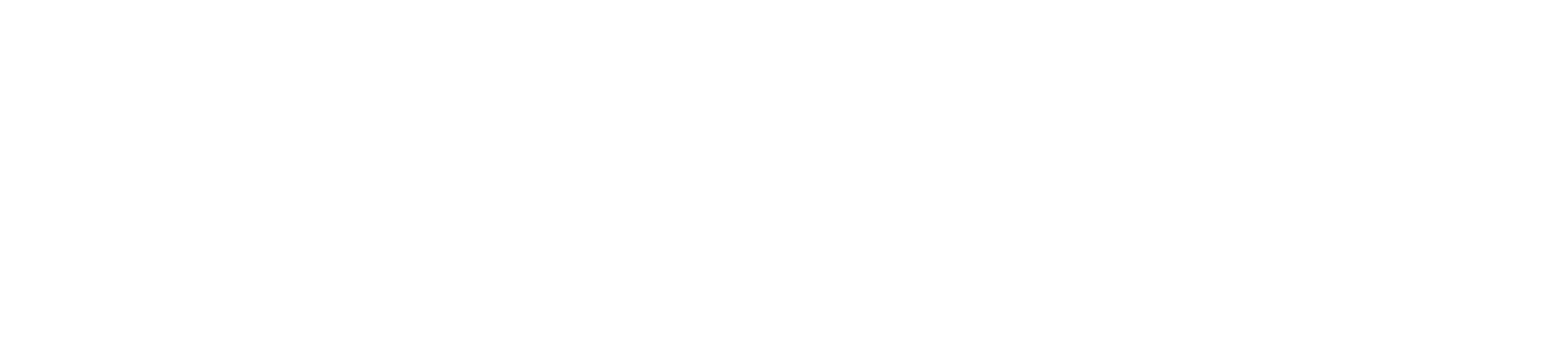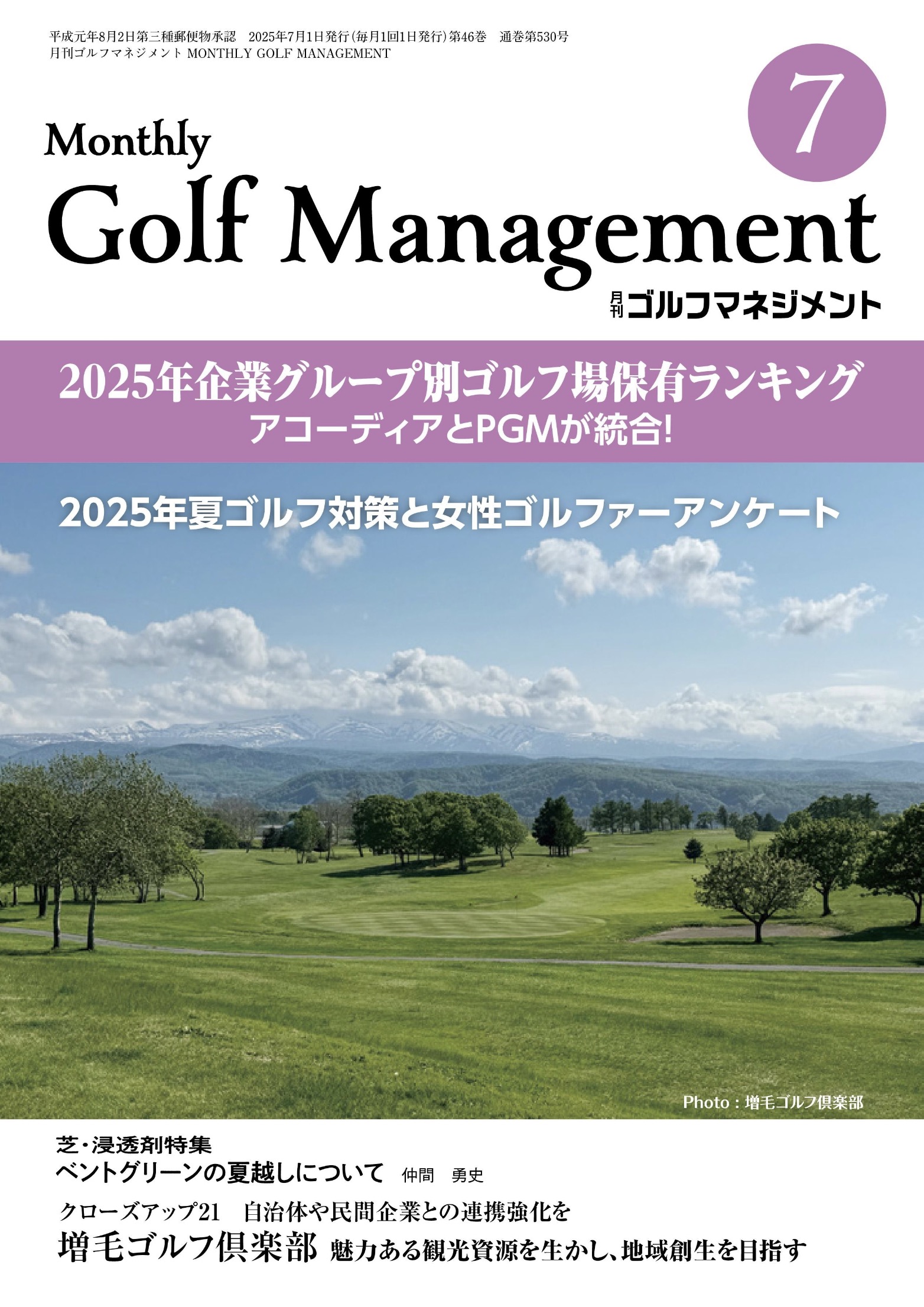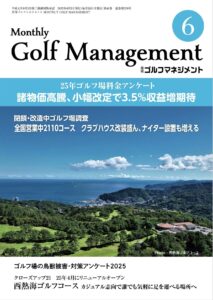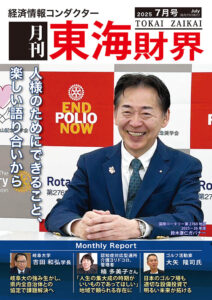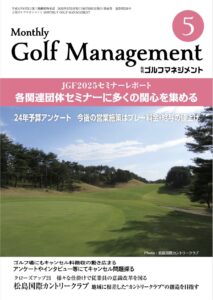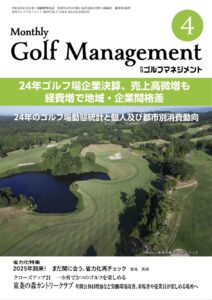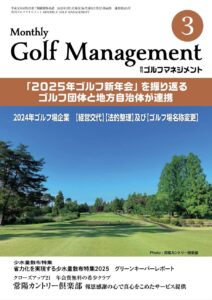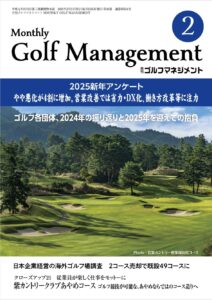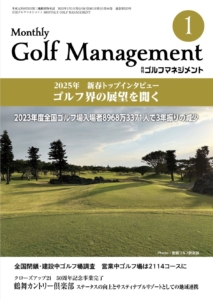ゴルフ界の総合経営誌『月刊ゴルフマネジメント』で、経営に関するコラムを連載させていただいております。
第5回はのテーマは『なぜゴルフ場の仕組化はうまくいかないのか?』です。
月刊ゴルフマネジメントに掲載された記事一覧は下記のリンクからご覧いただけます。
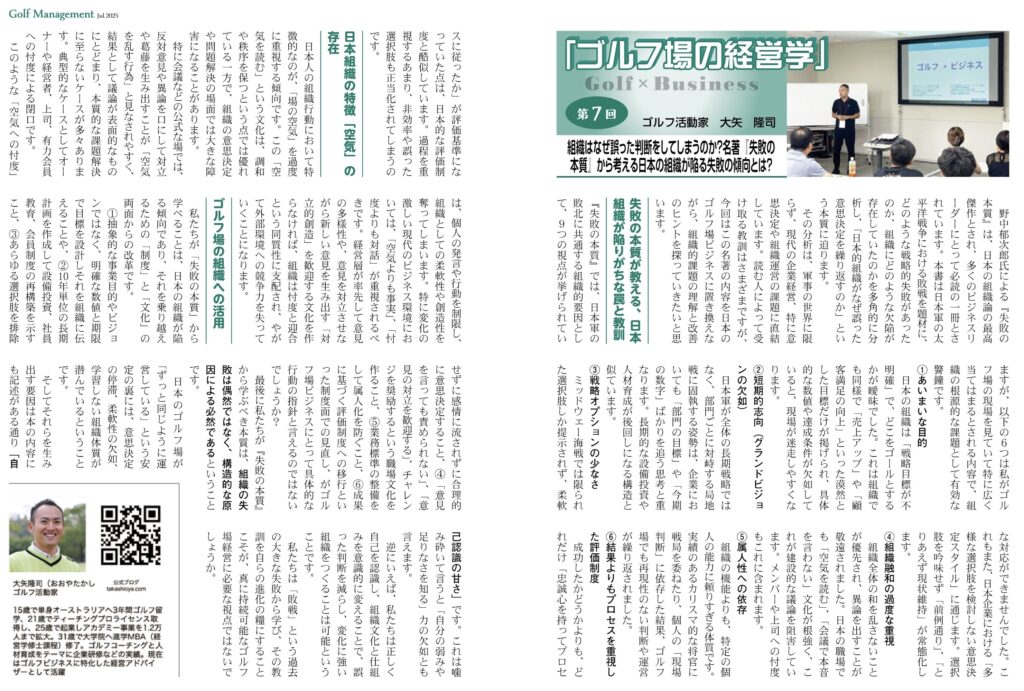
野中郁次郎氏による『失敗の本質』は、日本の組織論の最高傑作とされ、多くのビジネスリーダーにとって必読の一冊とされています。本書は日本軍の太平洋戦争における敗戦を題材に、どのような戦略的失敗があったのか、組織にどのような欠陥が存在していたのかを多角的に分析し、「日本的組織がなぜ誤った意思決定を繰り返すのか」という本質に迫ります。
その分析は、軍事の世界に限らず、現代の企業経営、特に意思決定や組織運営の課題に直結しています。読む人によって受け取る教訓はさまざまですが、今回はこの名著の内容を日本のゴルフ場ビジネスに置き換えながら、組織的課題の理解と改善のヒントを探っていきたいと思います。
失敗の本質が教える、日本組織が陥りがちな罠と教訓
『失敗の本質』では、日本軍の敗北に共通する組織的要因として、9つの視点が挙げられていますが、以下の6つは私がゴルフ場の現場を見ていて特に広く当てはまるとされる内容で、組織の根源的な課題として有効な警鐘です。
1. あいまいな目的
日本の組織は「戦略目標が不明確」で、どこをゴールとするかが曖昧でした。これは組織でも同様で「売上アップ」や「顧客満足の向上」といった漠然とした目標だけが掲げられ、具体的な数値や達成条件が欠如していると、現場が迷走しやすくなります。
2. 短期的志向(グランドビジョンの欠如)
日本軍が全体の長期戦略ではなく、部門ごとに対峙する局地戦に固執する姿勢は、企業においても「部門の目標」や「今期の数字」ばかりを追う思考と重なります。長期的な設備投資や人材育成が後回しになる構造と似ています。
3. 戦略オプションの少なさ
ミッドウェー海戦では限られた選択肢しか提示されず、柔軟な対応ができませんでした。これもまた、日本企業における「多様な選択肢を検討しない意思決定スタイル」に通じます。選択肢を吟味せず「前例通り」「とりあえず現状維持」が常態化します。
4. 組織融和の過度な重視
組織全体の和を乱さないことが優先され、異論を出すことが敬遠されました。日本の職場でも「空気を読む」「会議で本音を言わない」文化が根強く、これが建設的な議論を阻害しています。メンバーや上司への忖度もこれに含まれます。
5. 属人性への依存
組織の機能よりも、特定の個人の能力に頼りすぎる体質です。実績のあるカリスマ的な将官に戦局を委ねたり、個人の「現場判断」に依存した結果、ゴルフ場でも再現性のない判断や運営が繰り返されました。
6. 結果よりもプロセスを重視した評価制度
成功したかどうかよりも、どれだけ「忠誠心を持ってプロセスに従ったか」が評価基準になっていた点は、日本的な評価制度と酷似しています。過程を重視するあまり、非効率や誤った選択肢も正当化されてしまうのです。
日本組織の特徴「空気」の存在
日本人の組織行動において特徴的なのが、「場の空気」を過度に重視する傾向です。この「空気を読む」という文化は、調和や秩序を保つという点では優れている一方で、組織の意思決定や問題解決の場面では大きな障害になることがあります。
特に会議などの公式な場では、反対意見や異論を口ににして対立や葛藤を生み出すことが「空気を乱す行為」と見なされやすく、結果として議論が表面的なものにとどまり、本質的な課題解決に至らないケースが多々あります。典型的なケースとしてオーナーや経営者、上司、有力会員への忖度による閉口です。
このような「空気への忖度」は、個人の発言や行動を制限し、組織としての柔軟性や創造性を奪ってしまいます。特に変化の激しい現代のビジネス環境においては、「空気よりも事実」「忖度よりも対話」が重視されるべきです。経営層が率先して意見の多様性や、意見を対立させながら新しい意見を生み出す「対立的創造」を歓迎する文化を作らなければ、組織は忖度と迎合という同質性に支配され、やがて外部環境への競争力を失っていくことになります。
ゴルフ場の組織への活用
私たちが「失敗の本質」から学べることは、日本の組織が陥る傾向であり、それを乗り越えるための「制度」と「文化」の両面からの改革です。
①抽象的な事業目的やビジョンではなく、明確な数値と期限で目標を設計しそれを組織に伝えることや、②10年単位の長期計画を作成して設備投資、社員教育、会員制度の再構築を示すこと、③あらゆる選択肢を排除せずに感情に流されずに合理的に意思決定すること、④「意見を言っても責められない」「意見の対立を歓迎する」、チャレンジを奨励するという職場文化を作ること、⑤業務標準の整備をして属人化を防ぐこと、⑥成果に基づく評価制度への移行といった制度面での見直し、がゴルフ場ビジネスにとって具体的な行動の指針と言えるのではないでしょうか?
最後に私たちが『失敗の本質』から学ぶべき本質は、組織の失敗は偶然ではなく、構造的な原因による必然であるということです。
日本のゴルフ場が「ずっと同じように運営している」という安定の裏には、意思決定の停滞、柔軟性の欠如、学習しない組織体質が潜んでいるということです。
そしてそれらを生み出す要因は本の内容にも記述がある通り「自己認識の甘さ」です。これは噛み砕いて言うと「自分の弱みや足さなさを知る」力の欠如とも言えます。
逆にいえば、私たちは正しく自己を認識し、組織文化と仕組みを意識的に変えることで、誤った判断を減らし、変化に強い組織をつくることは可能ということです。
私たちは「敗戦」という過去の大きな失敗から学び、その教訓を自らの進化の糧にすることこそが、真に持続可能なゴルフ場経営に必要な視点ではないでしょうか。