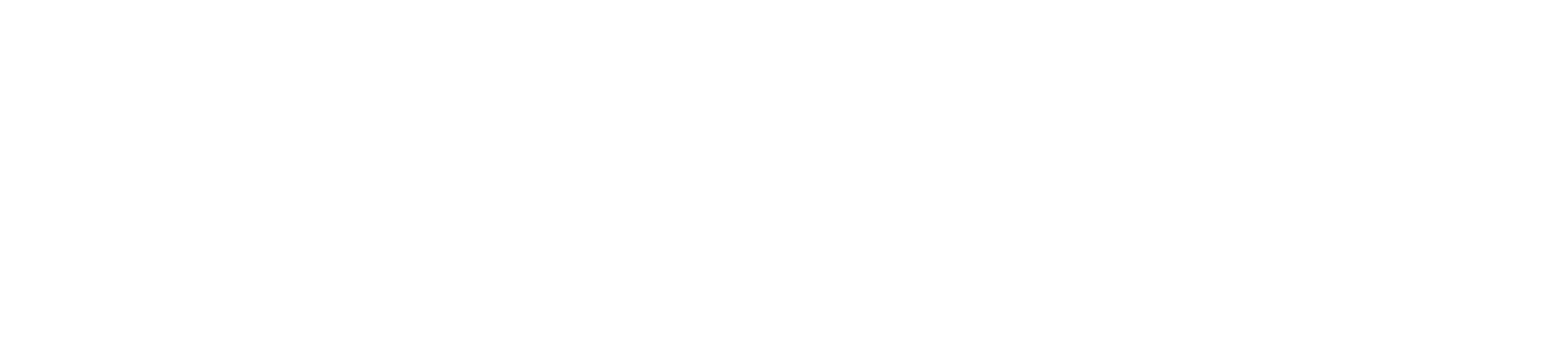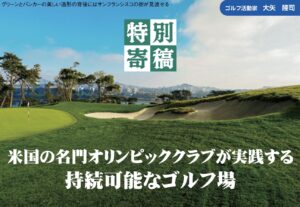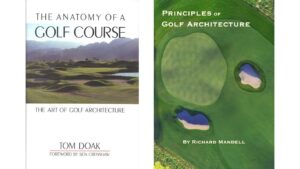人手不足を不安視する国内のゴルフ場において、18ホールの総面積40〜50万平方メートルとも言われる広大な土地を整備するコース管理スタッフを確保し続けることは、集客以上に深刻な関心事となっています。
その救世主として注目されているのが、「自動運転芝刈機」です。
自動運転芝刈機は人手を介さずに芝刈り作業を行えるため省力化効果が期待されますが、価格が高く投資に見合う効果が得られるのか疑問視する声も根強く、導入に踏み切ったゴルフ場はまだ限られています。
そこで今回は、USGA(全米ゴルフ協会)が発表したレポート「How Do Robot Mowers Affect Turf Management and the Golfer Experience?(自動運転芝刈機は芝生の管理とゴルファーの体験にどのような影響を与えるのか?)」を参考にしつつ、自動運転芝刈機の有用性や日本のゴルフ場産業への影響について考えてみたいと思います。
自動運転芝刈機とは?

自動運転芝刈機とは、芝生を自動で刈り込む無人走行型の芝刈機です。
この芝刈機は事前に設定したエリア内を決められたルートで自律走行し、業務時間外の深夜や早朝でも定期的に芝を刈り揃えることができます。
欧米では小型のバッテリー駆動式モデルが主流です。代表的なメーカーはスウェーデンのハスクバーナ社で、同社のAutomowerシリーズが欧米のゴルフ場やスポーツフィールドで広く導入されています。主力モデル「CEORA 546 EPOS」の価格は1台あたり約2万5千ユーロ(約450万円)とされています。

一方、日本ではスポーツターフ用芝刈機メーカーの共栄社のバロネスやTORO社、あるいは制御OSを開発するマミヤOP社などの自動運転芝刈機がシェアを獲得しています。
その価格は1台あたり2,500万〜3,000万円程度と言われていますが、2025年時点で約200コースで何らかの自動運転芝刈機が稼働していると言われています。
欧米と日本で異なるタイプの自動運転芝刈機が選ばれている背景には、利用目的の違いがあります。
日本では人による作業を完全に代替する手段として自動運転芝刈機を導入しようとする一方、欧米では自動運転芝刈機は既存作業を補助する役割として利用されているようです。
例えば、欧米で主流のバッテリー駆動式モデルのメリットとして「軽さ」や「静粛性」が挙げられます。これらの特性により、雨の翌日でもコース内にタイヤ跡を作らずに芝を刈ることができます。また、車体がコンパクトなため、大型機械が入れず従来は手作業で刈っていた林帯やティーエリア、急勾配でも使用が可能です。
一方、バッテリー駆動の弱点として長時間の連続使用が難しい点も指摘できます。
たとえば、ハスクバーナ社のプロ向けモデル「Automower 450X」でも、一度に作業できる面積は約5,000平方メートルほどで、カバーできる範囲が限られており、広いエリアを刈る場合は複数台が必要になります。
これに対し、従来からゴルフ場用芝刈機を製造してきたメーカーによる自動運転芝刈機は、ガソリン駆動で重量があり騒音も大きいものの、1度で5万平方メートル以上の刈り込みが可能です。そのため、従来は人が乗って運転していた9ホールや18ホール単位の芝刈り作業を、そのまま自動化できます。
自動運転芝刈機がもたらす省力化効果

最大のメリットは、何と言っても刈込作業の省力化です。
従来はコースを熟知した勤続年数の長い熟練スタッフが、早朝や夕方に何時間もかけて刈っていましたが、その作業を自動運転芝刈機は作業員が帰宅した後の夜間でも無人で自動的に行ってくれます。
USGAの調査では、自動運転芝刈機の導入によって顧客満足度や従業員満足度が向上したというデータも報告されています。その要因として主に以下のような点が挙げられています。
- 従業員の労働時間が削減され、芝刈りに充てていた時間を他の作業に回せるようになったことでコースコンディションが向上した
- 芝刈り頻度が上がり、常に良好なコースコンディションを維持できるようになった
- 芝刈り頻度の向上によって刈りカスが減少し、収集作業が不要になった
- 芝刈りの正確性が向上し、コースの美観が向上した
この調査からわかるのは、自動運転芝刈機のもたらす効果は、人件費削減といったコスト面よりも、芝の品質向上といった収益面において大きいということです。
自動運転芝刈機がもたらす省力化以外の効果

上述のように、自動運転芝刈機の導入は単に人件費を削減するだけでなく、コースのプレイアビリティ(プレーしやすさ)の向上や環境面での効果も期待できます。
USGAの調査によれば、ゴルファーの90%は自動運転芝刈機に対して肯定的または中立的な印象を持っており、その理由として「芝の状態が常に良好で安定していること」や「プレー環境が良くなること」などが挙げられています。
芝の刈り込み頻度が上がることで芝生がより密になり、ボールが沈みにくくなるためショットがしやすくなるという報告もあります。また、自動運転芝刈機による継続的な細かな刈り込みが芝生の健全性を高め、雑草や病害の発生抑制にもつながるという結果も示されています。
別のUSGAの研究でも、自動運転芝刈機で刈った区画では雑草や病害の発生が従来の手動刈り区画より少ないことが確認されています。
これは、頻繁な刈り込みによって葉面の加湿が抑えられ、植物へのストレスが軽減されること、さらに雑草の開花や結実が抑えられることが要因と分析されています。
雑草が減れば、当然ながら除草剤の散布回数を減らすことができます。
また、頻度が上がることで刈りカスが細かくなり、ブロワーの手間が減ることや、土壌中で有機分解されやすくなることで、土壌環境の維持にも影響します。
このように、自動運転芝刈機には、省力化だけではなく、プレイヤーの満足度向上や、環境負荷低減にも寄与する可能性が高いと言われています。
自動運転芝刈機を効果的に運用するための工夫
自動運転芝刈機の効果を最大限に引き出すには、運用上いくつか押さえておくべきポイントがあります。
まず、初期導入時の設置計画では、GPSやLTEの電波環境を調査し、作業エリアと走行ルートを設定するなど、入念な準備が必要です。
USGAの報告でも、導入に際してGPSおよびLTEの通信を確保するために樹木の伐採や走行経路の整備を行ったこと、新システムに作業員が習熟するまで時間を要したことなどが指摘されています。
次に、日常の点検・メンテナンスでは、ブレードの手入れを行い刃の切れ味を保つといった基本作業が欠かせません。また、導入台数が増えた場合には、それらを管理できる専任スタッフの配置も検討すべきでしょう。
さらに、自動運転芝刈機には安全機能が備わっており、障害物を検知すると自動的に停止するようになっています。その際、遠隔のスマートフォンなどの端末で安全を確認した上で再起動する必要があります。そのため、深夜の時間帯に作業を行わせていると、担当者が就寝中に万が一停止してしまった場合に再起動ができず、営業開始までに刈り込みが終わらないといった事態が起こり得ます。
最後に、筆者が最もお勧めする自動運転芝刈機の活用法は「フェアウェイの拡張」です。フェアウェイは、日本では通常18ホールで約10万平方メートルですが、欧米では14万平方メートル程度と、日本のフェアウェイはその約3分の2ほどの面積しかありません。フェアウェイが狭くラフや林帯が広いと、ティーショットの飛距離が低下したり、ボールを探す時間が増えたりして、プレーの満足度を下げてしまいます。そこで、フェアウェイを拡張してその部分の芝刈りを自動運転芝刈機に任せれば、人手で刈り込む面積を減らせるだけでなく、プレイヤーの満足度も向上するという一石二鳥の効果が期待できます。
投資費用対効果とまとめ
ゴルフ場の人手不足問題に対して、自動運転芝刈機は有望なソリューションになり得ると考えられますが、冒頭に書いた通り高額な費用を賄うほどの投資効果があるか?という点について最後に触れておきたいと思います。
一般的な5連のフェアウェイモアとの差額が1000万円だったとして、年間の刈り込み費やす時間を486時間(1ホール30分×18H×週2回×半年間)と仮定した場合、人件費換算すると約100万円(令和6年 賃金構造基本統計調査による正社員の月額平均賃金33万400円を160時間=時給換算額約2,063円)ということになりますから、投資回収期間は10年ということになります。
一方で、前述のようにフェアウェイを拡張して、その稼働時間を増やすことによって、投資効果が1.5倍になれば、投資回収期間は6.5年に短縮され、さらにプレイヤーの満足度が向上すれば、収益向上によるさらなる投資効果の向上も期待できます。
さらに刈込作業の無人化による省力化効果は言うまでもなく、常に安定したコースコンディションを維持でき、雑草・病害も抑制できるなど、自動運転芝刈機のメリットは非常に大きいものです。
こうした効果はUSGAのレポートや、海外の実証研究でも裏付けられており、ゴルファーからも好意的に受け入れられていると報告されていますから、まさに事業者・顧客・環境の三方良しのソリューションと言えるでしょう。
一方で、導入コストの高さや運用体制の整備、既存スタッフのスキル転換など、クリアすべき課題も残されています。導入にあたっては、コース規模に適した機種を選定し、試行期間を経て投資対効果や導入時期は慎重に見極める姿勢が求められます。
日本でも人材不足が深刻化する中、自動運転芝刈機が次世代のコース管理を担う「救世主」となる可能性は十分にあります。
すべてのゴルフ場が今後、その活用を積極的に検討する価値があるでしょう。