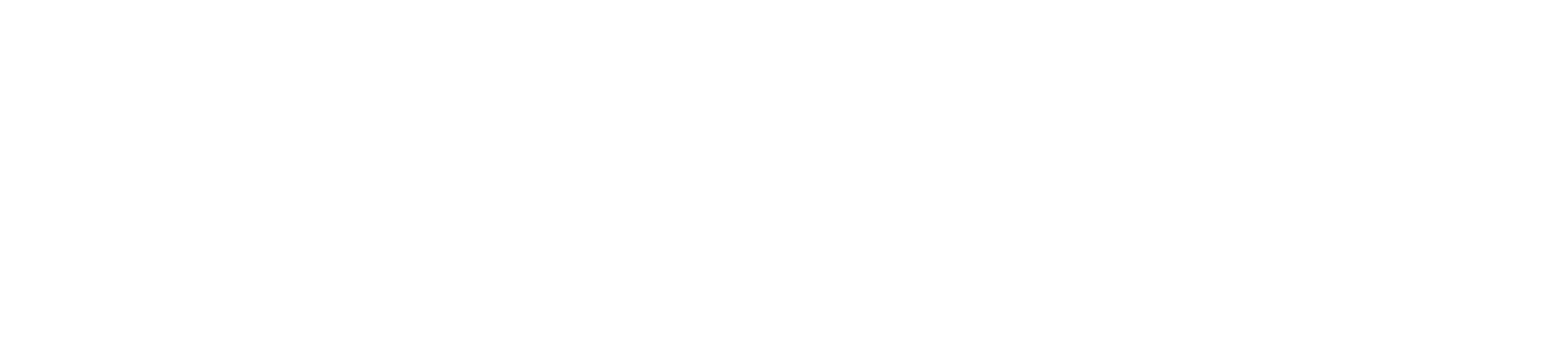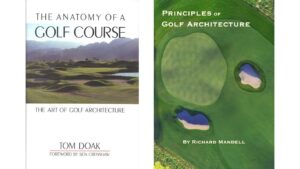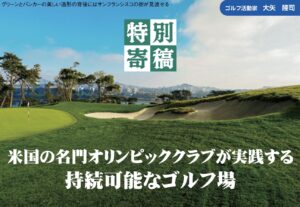ゴルフ場の特徴は一般的にその「見た目」で評価されることが多いのですが、それは正しい評価と言えるでしょうか?
確かにマウンドの美しい曲線美や、池のリフレクション、バンカーの白と芝の緑のコントラストはコースのデザインを決める重要な要素です。しかしデザインの要素で最も重要なのは、それぞれのアイテムの面積構成比という数字です。
今回はティーやフェアウェイ、バンカー、グリーンといったコース内の主要なアイテムの面積に焦点を当てて、コースの特徴を数字で読み解くという試みを記事にしました。
ゴルフ場建設に関わるコンサルタントならではのユニークな視点になっていると思いますので、ぜひお付き合いください。
1. 日本のゴルフ場の総面積は18ホールで約50万平米

18ホールのゴルフコースを造るには、一体どれくらいの土地が必要なのでしょうか?
一般的な目安として、日本では18ホールのゴルフ場は約50万平米前後の広さが必要だと言われます。
米国の調査によれば、米国の平均的な18ホールのゴルフ施設は中央値で60万平米の敷地を占有しており、その内訳はフェアウェイ、グリーン、ティなどの芝生アイテムが36%で21.6万平米、林帯やナチュラルエリアが26万平米、池や川が6.4万平米となっています(USGAによる調査)。またプレーエリアの中でも集中的に管理されるアイテム(ティ、フェアウェイ、グリーン)は14万平米と言われており、残りはラフや林帯など周辺環境ということになります。
最初に述べた通り、日本のゴルフ場の18ホールで50万平米という面積は山岳地形や用地の規制からコース全体の面積は米国の60万平米と比べると小さい傾向がありますが、古いリンクス系のコースやリゾートでは広大な100万平米以上を持つコースも珍しくありません。
2. ティーの面積はラウンド数で決まる

コースの「ティーイングエリア」は各ホールのスタート地点ですが、その広さは一般的に利用者数に見合った計画が求められます。
実はティーは利用者数に対して面積が不足すると芝の損耗が激しくなり管理上問題が生じます。年間を通じて多くのゴルファーが利用するコースほど、ティーエリアを広く取って使用エリアを分散させなければ、プレイヤーの歩行による踏圧と摩擦とディボットであっという間に激しく痛んでしまい、結果的にグリーンキーパーはティーマークを移動せざるを得なくなり、プレイヤーは自分の技量に合っていない距離からプレーすることになります。
このようにティーの広さはコースコンディションとプレー体験の双方に関わる重要な要素なのです。
GCSAA(全米ゴルフコース管理者協会)やUSGA(米国ゴルフ協会)は理想的なティーの面積として年間3万人がプレーする平均的なゴルフ場の場合で280平米/1Hが必要だと述べています。またASGCA(全米ゴルフコース設計家協会)は1ラウンドあたり0.15~0.20平方フィートのティーエリアを推奨しており同じく年間3万ラウンドの場合250~330平方メートルのティー面積が必要であり、パー3はディボット多発のためさらに25%程度の上積みが妥当とされています。
筆者は運用面では「もっとも使用が集中するミドル(レギュラー)ティーを広めに、バック/フォワードを小さめに配分して総管理面積を最適化」という合理的運用(たとえばミドル200㎡、バック/フォワード70㎡級など)を推奨していますが、これは各クラブの来場者構成に応じて調整してください。
3. 日本のゴルフ場のフェアウェイは狭すぎる?

フェアウェイの広さ(幅や面積)は、コースの難易度や戦略性のみならず、プレーヤーの満足度やプレー速度に大きく影響します。
一般的なフェアウェイ幅はコース設計や環境によって様々ですが、その幅は約25ヤードから65ヤード程度まで幅があります。世界的な中庸値としては35~45ヤード前後とされており、日本では30~40ヤード台が標準的なフェアウェイ幅と言えるでしょう。
計算上では標準的なPar.4のホールでは9万平米がフェアウェイ面積となりますから、Par.3を除くと12-13万平米/18Hが理想的なフェアウェイ面積となります。
フェアウェイが狭くなることの弊害は、フェアウェイキープ率が50%以下と言われる平均的なゴルファーにとってはボールを探す時間が増えたり、長いラフからのショットが難しくなって、プレーの進行が遅れたり、プレーヤーの満足度が低下したりすることが指摘されています。
長い間、特に日本の多くのクラブは、山岳地形や林間コースが多く地形的制約があることや、労働時間の節減のため、刈り込み頻度の多いフェアウェイ面積を減らす試みもありましたが、近年では自動無人モアの登場もあり、逆にフェアウェイを広げることで人的資源を投入する管理面積を減らすことができることから、フェアウェイ幅は拡張傾向にあります。
実際に筆者は、いわゆる「無人機」の最大の利点は、管理の省力化と顧客満足度という従来相反する2つの要素を、「フェアウェイエリアの拡張」を実現することで、同時に達成できることにあると考えています。
もちろん戦略的に意図された「絞ったフェアウェイ」が特色の名コースもありますが、ビジネス的視点で言えば極端に狭いフェアウェイはプレーヤーのプレー満足度を損なうリスクとして捉える必要があります。
日本のゴルフ場経営者にとって、自コースのフェアウェイ幅が世界的に見て適切なレンジに収まっているかを数字で把握することは、課題発見の第一歩と言えるでしょう。
4. バンカー面積は広ければ広いほどコストがかかる

白い砂が映えるバンカーはコースの景観にメリハリを与え、戦略性を高める要素ですが、その面積と維持コストの関係にも着目しなければなりません。
一般的にバンカーはコース内で最も維持にコストがかかるアイテムだとされています。
USGAグリーンセクションの報告では、バンカーの多いコースでは週平均にすると200〜450時間もの人手をバンカー整備(レーキがけ、雨後の修復、縁刈りなど)に費やしているとのことです。これは金額に換算すると、平均300時間/週をバンカー整備に費やしていると考えると、年間では1500万円程度の労務費に推定され、グリーン維持よりもバンカー維持の方が費用がかさんでいるというケースも珍しくありません。
バンカーはこうした日常的メンテナンスに加えて、砂の補充や洗浄、法面の整形、排水機能の維持など数年おきの更新にも手間がかかる上、近年ではライナー(砂の下に敷く特殊なシート)や砂など資材コストも増大しています。
これらはバンカーの総面積にほぼ比例してコストが膨らむため、バンカーを設計する際には「面積=維持コスト」であることを念頭に置く必要があります。
このようにバンカーはグリーンやフェアウェイ以上に労力と費用を要するにも関わらず、USGAが全米のプレイヤーに行ったアンケートによると、バンカーは常にプレイヤーの不満要因の上位に挙げられています(砂が硬い、足跡、水たまりや雨裂など)。
労力とお金をかけて不満を増幅させては本末転倒です。
私は日本のゴルフ場のコース管理の負荷が高い理由の一つに2グリーンシステムによるバンカー面積の広さが関係していると考えています。
平均的に1グリーンのコースの18Hのバンカー面積は8000平米程度と言われていますが、日本の2グリーンはガードバンカーが単純に2倍になるので、コースのバンカー面積は15000平米以上になります。

5. 最適なグリーンの広さはどれくらい?

ゴルフコースの「グリーン」は、プレーヤーが最後にパッティングをする非常に重要なエリアです。その広さ(面積)はコース設計の哲学や戦略に応じて様々ですが、「最適な大きさ」はどれくらいなのでしょうか?
一つの目安となるのが、米国USGAがまとめた平均的なグリーンサイズのデータです。最近のUSGAの調査によれば、全米のゴルフコースにおける平均的なグリーンの大きさは約520平米と報告されています。
カリフォルニアの名門ペブルビーチ・ゴルフリンクスはグリーンが非常に小さいことで有名ですが、平均グリーンサイズは325平方メートル程度しかありません。
逆にワシントン州のチャンバーズベイはグリーンが巨大なことで有名で、平均約836平米にも達します。
同じ18ホールでも、コースによってこれほどグリーンの広さが違うのは驚きかもしれませんが、実は広い方が良いのか、小さい方が良いのかという論争には意味がありません。
小さいグリーンはターゲットが絞られるため難易度が上がり、またカップを切れるエリアが限られる分グリーンが傷みやすいというデメリットがあります。
また狭いエリアで傾斜に変化を持たせるためには、必然的に勾配がキツくなるため、高速グリーンには不向きになります。
一方、大きいグリーンは多彩なピンポジションによる高い戦略性が提供できますが、その分管理コスト(施肥、散水面積、刈込労力)が増えます。
一概に理想的なグリーンサイズを語ることは難しいですが、例えば短いパー3や2オン可能な短いパー5ではグリーンを小さくして精密なショットを要求し、長いパー4ではグリーンを大きめにして遠距離からでも乗せやすくするなど、戦略性と合理性を高い次元で融合させる多彩なサイズをもったグリーンが理想といえます。
6. コースの特徴や課題は見た目ではなく数字で見る

いかがでしたか?
今回の記事ではゴルフコースを構成する主要アイテムを面積という数字の観点から見てきました。
ゴルフ場の評価や運営上の課題は、本来見た目や印象だけで論じられるものではありません。むしろ数字という共通言語を通して客観的にコースの真実を捉えることで、初めて浮かび上がる認識や改善点が見えてきます。
例えば、漠然と「うちのコースは狭い林間で難しい」という印象を抱いていても、実際にフェアウェイ幅を計測して平均値と比較すれば、具体的に何平米狭いのか、何平米広げればいいのかが分かります。それによって適切なフェアウェイラインの変更や伐採、ティーの増設などの検討が可能になり、会員や顧客満足度を高めることができます。
同様に、バンカーの総面積やグリーン1面あたりの広さをデータ化し業界ベンチマークと比べることで、自コースの課題や特徴が客観的に把握できます。
実際、USGAの大規模調査では近年の新設コースほどバンカー面積やグリーン面積は減少する傾向が確認されています。これはこうした分析技術の進歩や戦略思想の変遷によりコース設計のトレンドが変わってきたことを示すもので、数字を分析することでゴルフ場の進化まで読み取れるプラクティスです。
ゴルフ場経営においては、「面白いコースを作る」「美しいコースを作る」ことと同じくらい「数字に強い」視点を持つことが求められています。
コースの各要素について、その面積・割合・コストといったデータを把握し、定量的に評価することで、見た目だけでは分からない自コースの強みや弱点が見えてきます。
最後に、こうした定量評価のメリットは、明確な数値基準による客観性と公平性の高さ、結果の明確さによる分かりやすさと評価の簡潔さ、データ蓄積・分析による効率的な改善です。
コースの特徴や課題のほとんどは見た目や印象など情緒的に語られがちですが、ゴルフ場経営者の方は、ぜひ曖昧な印象に引っ張られず、コースを数字で見る習慣をつけてみてください。
それが結果的に、ゴルフ場の健全な運営とプレーヤー満足度向上につながる科学的アプローチとなります。