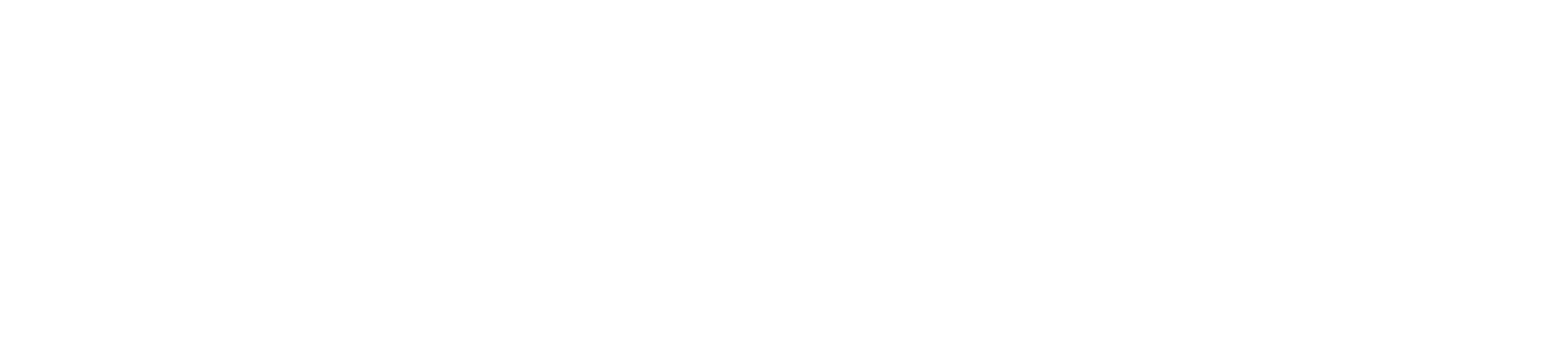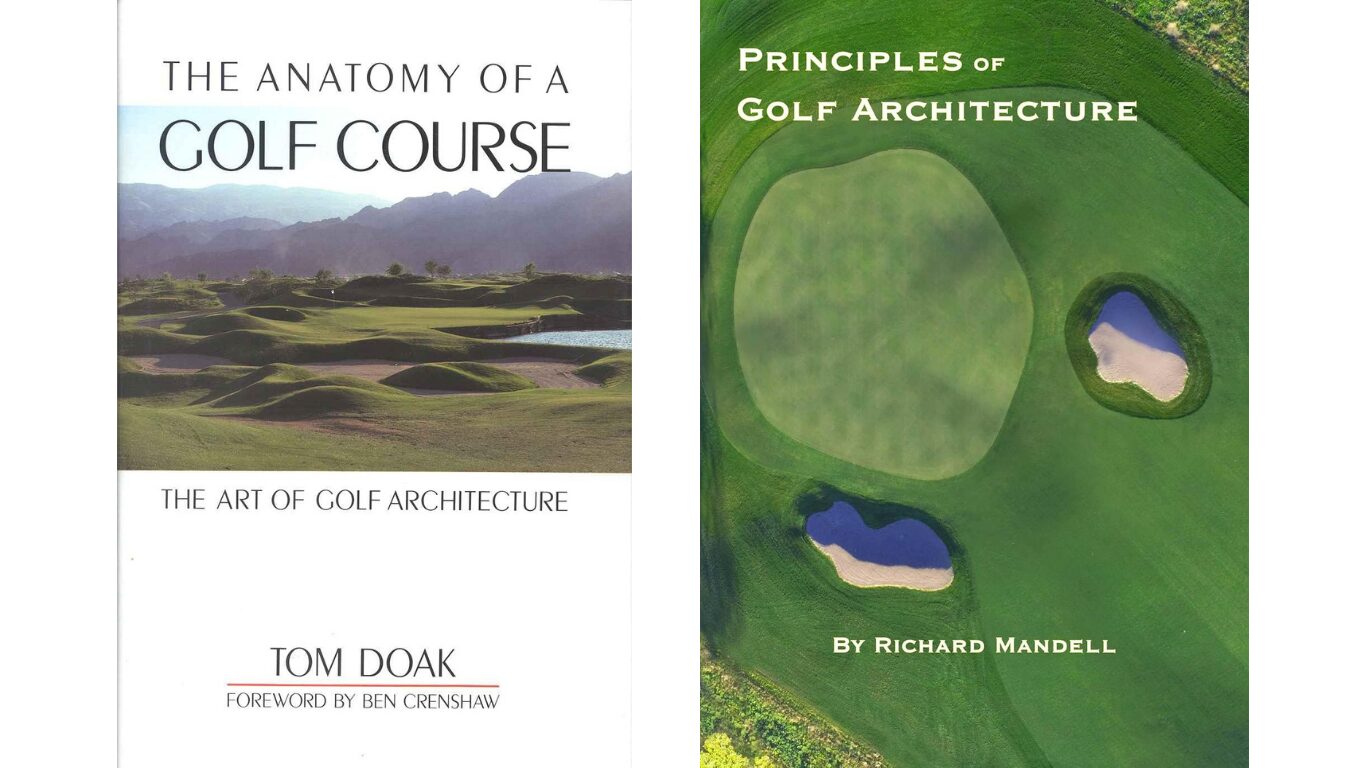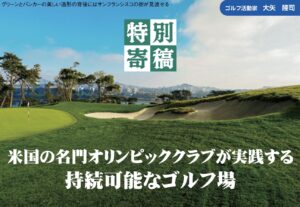コースの老朽化に伴いコースの一部、あるいは全面改修の相談が増えています。
その過程で「管理費削減のためにバンカーを減らしたい」、あるいは「プレー進行のためにフェアウェイを広げたい」など、コースのデザインを変更することで、利益や付加価値を高めるコース改修について相談を受けることがあります。
しかしデザインの変更によってコースの魅力が失われてしまっては本末転倒であるにも関わらず「良いゴルフコースデザインとは?」という問いには、専門家に相談しても、抽象的で主観的な回答が多く散見され、施主である経営者やオーナーからすると「良いゴルフコース」の定義が分からないというのも事実です。
このコラムでは、ゴルフ場の改修工事や運営に携わり、世界の名門コースを見て回ってきた経験がある筆者が、「良いゴルフコース」の定義や評価軸を、ゴルフ業界関係者はもちろん、一般ゴルファーにも分かるレベルで明確にする目的で書いたものです。
また本稿の執筆において、「良いゴルフコース」という曖昧な内容に対して、私の主観性を排除するために、ゴルフ場建設のバイブルと呼ばれるTom Doak氏の『The Anatomy of a Golf Course』や、Richard Mandell氏の『Principles of Golf Architecture』の中から、特に重要だと思われる部分を参照しました。
この文章が多くのゴルフ場関係者の方に読まれ、日本に「良いゴルフコース」が一つでも多く増えることを願っています。
ゴルフコース設計の歴史と重要な設計者たち

筆者撮影
ゴルフコース設計の歴史は19世紀のリンクスコースの古典期に始まり、 20世紀初頭にゴルフ場建設の黄金期を迎えました。この時期にはハリー・コルトやドナルド・ロス、アリスター・マッケンジー、など数多くの名匠が登場し、その思想と哲学は21世紀の現代においても高く評価されています。
例えばドナルド・ロスは生涯で400以上のコースを設計し、戦略的なデザインとプレーヤーの楽しさを重視したと言われています。アリスター・マッケンジーはオーガスタ・ナショナルやサイプレス・ポイントに代表されるコースを設計し、自然美とプレイのしやすさの調和を追求したことで知られます。こうした黄金期の設計思想(ストラテジックなデザインや景観との調和など)は、現代にも通じるゴルフ建築の基本となりました。

筆者撮影
第二次世界大戦後はロバート・トレント・ジョーンズSr.が台頭し、大型重機の登場とも重なり、大規模な造成と池やバンカーを多用した「チャンピオンシップコース」スタイルが広まりました。彼はクラブの技術革新とテレビ中継に対応するため、コースを難しくし近代化することで成功を納めた設計家で、代表作スパイグラス・ヒルなど多くのコースを手掛けました。
このヒーロイックなデザイン手法は、加速度的に普及した「テレビ映え」と相まって一時期主流となりましたが、同時に平均的ゴルファーには過剰な難易度との批判も招きました。
1970年代以降になるとピート・ダイやミュアヘッドに代表される近代設計者たちが登場し、鉄道の枕木をバンカー縁に使うといった独創的アイデアや視覚的トリックを駆使したコースでゴルファーを驚かせました。TPCソーグラス(スタジアムコース)のアイランドグリーンなどがその好例で、エキセントリックな視覚的インパクトと戦略性が融合したデザインは「ターゲットゴルフ」と称されました。

筆者撮影
そして1990年代後半以降、ゴルフコース設計は「ミニマリズム」と呼ばれる潮流が注目を集めます。
トム・ドークやビル・コア&ベン・クレンショー、ギル・ハンスら現代の名匠は、可能な限り造成を減らし自然地形を活かす手法で名コースを生み出しています。

筆者撮影
トム・ドークは自ら「世界中の名コースを1000以上見て学んだ」経験を設計に活かすと言い、彼の設計哲学はミニマルかつ戦略的なデザインにあります。例えば彼の代表作であるパシフィック・デューンズは自然の砂丘地形を巧みに使った戦略的レイアウトで高い評価を受けています。また、こうした現代の設計者に共通するのは、前述のロスやマッケンジーといった黄金期の理念への回帰です。歴史を敬いつつ最新技術を活用したリストレーション(復元)やリデザイン(改修)にも力を入れ、クラシックコースの良さを蘇らせる動きも盛んです。
このように、ゴルフコース設計の歴史は自然との調和と戦略性を追求してきた流れと、難易度や演出を追求した流れのせめぎ合いと言えます。今日では両者のバランスをとりながら、「時代を経ても色褪せないコース」を目指すことが良いゴルフコース設計の基本となっています。
ゴルフコース設計における3つのコンセプト:「ペナル」「ヒーロイック」「ストラテジック」
ゴルフコースの設計思想には古くから大きく3つの典型的コンセプトがあるとされます。
ペナル・デザイン(Penal Design)、ストラテジック・デザイン(Strategic Design)、ヒーロイック・デザイン(Heroic Design)、 の3つです。それぞれの特徴を簡潔に説明します。
ペナル・デザイン(Penal Design)

ミスショットは即ペナルティに繋がるデザイン
ペナルとは「罰則」を意味し、その名の通り間違ったショットに対し容赦なくペナルティを課す設計手法です。
一つのホールに「正しい攻略ルート」が一つ定められており、要求されるショットを正確に打てれば報われますが、外せばその程度に応じて厳しく罰せられます。例えばティショットはフェアウェイ中央へ真っ直ぐ打たなければならず、左右に外せば深いラフやハザードが待ち受ける、といった具合です。上級者には肉体的な技術を極限まで要求するため挑戦的ですが、平均的なゴルファーには一辺倒で息苦しいレイアウトになりがちで、「プロには楽しくても大衆にはあまり魅力的でない」とも評されます。
19世紀末から20世紀初頭、ゴルフが競技として広まると同時に、それまで主流だった1対1のマッチプレー方式から、多人数が同時にプレーをして順位を競うストロークプレー方式が主流となったことから、一部のこの頃の設計者はスコアの差を付けるためには罰を与えるコースこそが良いと信じていました。
しかし近代では、一方通行で融通の利かないペナル設計は敬遠されがちで、強制的に越えねばならない障害ばかりではなく、選択肢を与えるデザインの方が望ましいと考えられています。
もっとも、ペナルなホールにもラウンドのスパイスとしての価値はあり、18ホールの中で適切に配置すればコース全体のメリハリを生むため、完全に排除すべきものではないとも言えます。
ストラテジック・デザイン(Strategic Design)

筆者撮影
ストラテジックとは「戦略的」という意味で、その名が示す通りプレーヤーに複数の攻略ルートや選択肢を与える設計手法です。
20世紀初頭、セント・アンドリュース(オールドコース)の戦略性に着想を得て生まれたスタイルで、ペナルデザインの一面的な攻略法に対するアンチテーゼとして発展しました。各ショットごとにリスクを多く取る攻め方と安全に行く守り方が用意されており、プレーヤーは自分の技量やその日の調子に合わせてリスクとリワード(報酬)のバランスを判断します。
例えばティショットでバンカー越えの近道を選べば次打が楽になるが失敗すれば罰を受け、無難に遠回りすれば即座の罰は無いが次打が長く残る、といった具合です。要するに「高リスク・高リワード」と「ローリスク・ローリワード」の複数経路を設計者が意図的に作り込み、ゴルファーに知的な判断を促すデザインです。
この考え方は現代のゴルフコース設計で最も重視されるコンセプトと言ってよく、多くの名コースが何らかの形でストラテジックデザインの要素を持っています。ストラテジック設計は、ゴルファーの頭脳(思考)と技術の両面を引き出すため、飽きの来ないゴルフを提供できる点が優れています。
ヒーロイック・デザイン(Heroic Design)

筆者撮影
ヒーロイックは「英雄的な」という意味で、ゴルファーに大胆なチャレンジを促す設計手法です。
基本的にはストラテジックデザインの一種ですが、特にラウンド中のどこかで「英雄的な1打」を要求する避けられない試練を設ける点が特徴です。
このコンセプトは第二次大戦後にロバート・トレント・ジョーンズSr.が自ら「新しい設計思想」と謳って広めました。彼はウォーターハザードなどを駆使して、プレーヤーが勇気を振り絞らなければならない場面をコースに組み込んだのです。
例えば最終18番ホールで池越えのロングショットを強いるような設計が典型で、「最大限に大胆なショットを成功させれば勝利(ご褒美)を得、失敗すれば悲劇(大きな罰)を味わう」ような劇場型の演出がなされます。
ヒーロイックデザインのホールでは、プレーヤーの勇気が試され、成功すれば強い達成感が得られる一方、失敗すれば大叩きとなるため記憶に残る経験を提供します。ただし無謀に難易度を上げるだけでは良いホールにならないため、ヒーロイックな要素も適度な逃げ道や救済措置と組み合わせることが重要です。
実際の名コースを見渡すと、これらペナル・ストラテジック・ヒーロイックの要素がバランス良く織り込まれ、この多面的な魅力が「バラエティの豊かさ」として高く評価され、「良いゴルフコース」と言われます。
別の言い方をすれば技術=ペナル、判断=ストラテジック、勇気=ヒーロイックの全てが詰まっており、それらが絶妙なニュアンスと複雑性の中で融合することで、18ホールが奥深い物語となるのです。
ゴルフコースを評価する主要項目

筆者撮影
「良いゴルフコース」を客観的に評価するには、複数の観点から見る必要がありますが、ゴルフコース評価の軸は一般的に以下のような項目が挙げられます。
戦略性と多様性
コースが 戦略的な挑戦 を提供しているか、ホールごとに異なるプレー体験が用意されているかは重要な評価となることは前章で伝えた通りです。
さらに付け加えるとすれば、戦略的な挑戦や多様性が、老略男女や巧拙に関わらず、すべてのプレイヤーに提供されていることが重要です。
景観美と自然との調和
コースの美しさや雰囲気も評価に欠かせません。
優れたコースは単に木々や花が美しいだけでなく、周囲の自然景観(借景)と一体化したデザインであることが重要です。
名匠マッケンジーも「人工の造形物は自然そのものに見えるべきだ」と述べている通り、人工的に造成された部分もあたかも最初からそこにあった自然地形のように見えることが理想であり、印象的に残る(メモラビリティ)かどうかも評価を高める要因です。
高評価のコースには、海岸線を望む絶景や、圧倒的な眺望を持つコースが多いのは、その美しい景観がゴルファーの記憶に強く残り続けることが理由です。
公平さ・プレイアビリティ
コースの難易度設定が適切か、幅広いゴルファーが楽しめる配慮がなされているかも重要なポイントです。
フェアネス(公平さ)とは、上級者にはチャレンジを提供しつつも、初心者やハイハンデのプレーヤーにも過度な理不尽さを強いない設計になっているかということです。
具体的には、リスクを取らない安全策を選べば大叩きは避けられるよう逃げ道が用意されていたり、各ホールに複数のティーグラウンドを設けて飛距離や技量に応じた距離でプレーできるようにしてあったりすることが挙げられます。
実際、現代のコースではバックティからフロントティまで5種類以上のティー設定を持つことも珍しくなく、誰もが適切な難易度でラウンドできるよう工夫されています。
またボールが無くなりにくい設計もプレイアビリティの一部です。
深すぎるラフや理不尽なブッシュ、林帯を避け、OBやロストボールでプレーヤーがストレスを感じないようにすることは、ラウンドの満足度に直結します。実際マッケンジーも「球探しによる苛立ちのないコースであること」を理想条件に挙げています。
コースのプレイアビリティはビジネス的にも重要で、常にボールの落下地点が視認できて、ストレスなく楽しめるコースほどリピーターが増える傾向があります。
コースレイアウトのバランスと流れ
18ホール全体として見たときの構成も評価項目です。パー3・4・5の配分、ホールの長短や向きのバリエーション、難易度の起伏などがバランス良く配置されていることが望ましいとされます。
例えば、似たような長さや方向のホールが連続せず、左右へのドッグレッグや上り下りのホールが程よく交錯しているか、アウトとインで風向きが偏らないか、といった点です。
さらにルーティング(コースの配置・順番)が論理的でプレーヤーの導線に無理がないことも大切です。ホール間の移動距離が長すぎず繋がりがスムーズで、各ホールが地形のベストな部分を活かして配置されている場合、ラウンド全体の体験が向上します。
ロバート・トレント・ジョーンズJr.は「優れたルーティングは良く仕立てられたスーツのようなもの。最初の裁断が悪ければ最後までうまくいかない」と述べています。すなわち、コース全体のストーリー性やペース配分がプレーヤーを飽きさせず高揚させるよう設計されていることが、良いコースの条件になるのです。
メンテナンス状態(コンディション)
いかに設計が素晴らしくても、芝生の状態が悪かったり、グリーンがデコボコで転がりが不揃いだったりしては台無しです。したがって、高品質の芝生コンディションを維持できているかも評価の重要項目です。
フェアウェイやグリーンが年間を通じて良好な密度と速さを保ち、バンカーには適切な砂が入って均一に手入れされているか、ティーグラウンドが平坦で剥げていないか等がチェックされます。
マッケンジーも理想の条件として「コースは夏冬いずれの季節でも良好であるべき」「グリーンとフェアウェイの芝質は完璧で、グリーン手前のアプローチもグリーン同様のコンディションが保たれるべき」と述べています。良いコースはこの言葉通り、雨季でも水はけが良く冬でも芝が枯れにくいなど、整備の質と設計上の工夫によって安定したコンディションを実現しています。
以上のような 戦略性、美観、フェアネス、多様性、レイアウト、メンテナンス といった主要項目が総合的に優れているコースこそ、「良いゴルフコース」と評価されます。
もちろんそのコースが持つ歴史的価値や地域の文化との関わりなど定量化しにくい要素もありますが、デザイン面においてはこれらが評価の軸となります。
設計者リチャード・マンデル氏も自身の著書でバランス、リズム、コントラスト、強調、多様性、偶然性、意図、挑戦、公平さ、シンプルさ等、実に35もの設計原則を挙げていますが、それだけ多角的な視点でコースを見ることが大切だということでしょう。
ゴルフ場経営者やオーナーは、自社のコースがこれら主要項目でどのような客観的評価を受けうるかを常に意識する必要があります。
「造形(シェーピング)」の重要性

筆者撮影
ゴルフコースの造形(シェーピング)とは、地形の造成やグリーン・バンカーの形状を作り込む作業を指し、コースデザインの中核を成すものです。
優れた造形は、単に地面を平らに均すだけではなく、美観(見た目の美しさ)・戦略性・プレイアビリティの三要素すべてに直結する重要な役割を果たします。
まず戦略面では、土地の起伏や傾斜の付け方ひとつでホールの難易度や攻め方が大きく変化します。
例えば名設計家ドナルド・ロスは、グリーン周りの地形に微妙な起伏を与えることで、ゴルファーの心理に揺さぶりをかけるデザインを特徴としました。
造形はコース建設のキモであり、グリーン形状やフェアウェイの傾斜をどう造るかで、コースのキャラクターが決まると言っても過言ではありません。
美観の面でも造形の果たす役割は大きいです。ゴルフコースは自然の景観を楽しむ場でもあり、その中に人工的な要素(グリーンやバンカー、池の縁など)を違和感なく溶け込ませる必要があります。
優れたコースではバンカー一つとっても周囲の地形と一体化するような自然な造形がなされますが、人の手で造成した部分をいかに自然に美しく見せるかはシェイパーの腕の見せ所です。
例えばリンクスコースのように砂丘地帯に造られたコースでは、バンカーの縁を不規則にギザギザにすることで、まるで風で浸食された砂地の穴が偶然そこにあるかのような外観に仕上げたりします。また、ティーグラウンドの盛土も周囲の地形につなげて緩やかにぼかすことで、景観を乱さない工夫がなされます。造形によって生まれる陰影やラインの美しさがコース全体の印象を左右し、結果的に評価やブランド価値にも関わってきます。
さらにプレイアビリティ、つまりプレーしやすさにも造形は影響します。
例えばフェアウェイの微妙な傾斜を調整してボールがフェアウェイ中央に集まりやすくすることで初心者でも球を捜しやすくしたり、グリーン周辺の不公平なキックを減らしたりといった配慮は、すべて造形の妙により実現できます。
逆に、造形のまずさはプレーヤーに不満を与えます。適切な勾配で作られていないスロープでは雨水が溜まりボールが埋まってしまうでしょうし、グリーン上の傾斜が強すぎればパットが不当に難しくなります。適切な造形とは、単に戦略的・美観的なだけでなく、機能的(ファンクショナル)にも優れていることが求められるのです。
以上のように、ゴルフコースにおける造形の重要性は計り知れず、優れた造形なくして優れたコースなしとも言えるでしょう。
デザイナー(設計者)と、アーティスト(シェイパー)が綿密に連携することで、グリーン1つ、バンカー1つの形状や繋がりまで細部を丹念に作り込むことで、プレーヤーが視覚的に感動し、頭脳的に挑戦され、かつ公平にプレーを楽しめる舞台を作り上げるのです。

筆者撮影
ゴルフコースを構成する「4つの基本アイテム」と達成されるべき重要な要件
ゴルフコースは様々な要素から成り立ちますが、中でもティー・フェアウェイ・バンカー・グリーンの4つは、コースを構成する重要アイテムです。
それぞれについて、設計上・運営上達成されるべき要件を解説します。
ティー(Tee)

筆者撮影
ティーグラウンドは各ホールのスタート地点であり、コースと対峙する第一印象を決定づけます。
「良いティー」にはいくつかの条件があります。まず平坦であること。
ティーがデコボコでは正しいスイングができず不公平です。次に十分な広さと複数のティーポジションを備えること。これによってコースは可変性を持ち、プレーヤーの力量や風向きに応じてティー位置を前後させられます。現代では「マルチティー」による難易度調整が標準であり、一つのホールに長短複数のティーを用意し、例えばバックティからフロントティまで距離差を設けることで、上級者から初心者まで誰もが楽しめる設計が求められます。
またティーの向きや高さも重要です。優れた設計では、ティーグラウンドがホールの狙い所に対して適切に角度付けされ、プレーヤーが次打であるフェアウェイやハザードなどのターゲットを視認しやすいよう高さも配置されています。
さらにティーはコース全体のメンテナンス計画にも関わります。
小さすぎるティーは同じ場所ばかり使用され芝が摩耗するため、十分な面積を確保しローテーションさせることで年間を通じた芝生養生を可能にします。加えて、ティーマーカーの設置によるコース設定の柔軟性も大切です。トーナメントではピン位置と同様にティー位置の組み合わせでコース難易度を調節します。
ティーはコースの中で唯一可変可能なアイテムであるため、そのホールにおける「舞台装置」として、距離・形・向き・高さを駆使してホール全体の特徴を演出します。
フェアウェイ(Fairway)

筆者撮影
フェアウェイはティーショットの落下地点からグリーン手前まで伸びる主要な平坦地帯で、ゴルファーにとっては「安全地帯」となるべきエリアです。
「良いフェアウェイ」にはまず適切な幅が求められます。
幅が狭すぎると常にラフや林に捕まり初心者には厳しくなりすぎます。一方、広すぎると上級者には単調です。
理想的には、ハンディキャップの高いプレーヤーでも無理なくボールを運べる十分な幅を持ちつつ、上級者には狙う場所(ベストポジション)を絞らせるよう要所でフェアウェイ幅が変化する菱形構造が理想とされます。
例えば「良いコース」と言われるコースでは、ティーからグリーンまで一様な幅ではなく、IPやハザード付近では絞られ、その手前のセーフティゾーンでは広がるといったメリハリが見られます。
また形状も重要で、完全な平坦ではなく、適度なうねり(アンジュレーション)があるフェアウェイは、球のライの変化により戦略性を増します。
グリーンの形状にリンクさせながらフェアウェイを傾けることで(例えば奥行きの狭いグリーンに対して左足下りのスロープにする、斜めに伸びたグリーンに対してドローやフェードを打ちやすくする)、戦略性を向上させます。
ただし極端な傾斜や丘登りは好ましくなく、特にランディングポイントでは歩行やカート移動の面でも負担が少ない3%から10%程度の範囲内で設計することが理想とされます。
芝生のコンディションもフェアウェイ評価の大きな要素です。
フェアウェイはプレイヤーにとっての安全地帯となっていますから、プレーヤーはフェアウェイに打ちさえすれば快適にショットできるという信頼感が必要であり、シーズンを通じて密で均一なターフを維持することが重要です。、
ディボット跡の補修はもちろん、雨後でも泥濘まないしっかりした土壌基盤や排水設計もフェアウェイの品質を左右します。
フェアウェイには表面排水を考慮して適度な傾斜をつけ、低い窪地には排水(暗渠排水や集水桝)を入れるなどして、水はけを良くすることが必須です。
「良いコースの3条件は排水、排水、排水」とまで言われるほど、フェアウェイの水捌けはコースクオリティの根幹をなします。
ここまで見てきて分かる通り、残念ながら日本のゴルフ場でよく見られる平坦で均一幅のフェアウェイや、フェアウェイの中央に樹木がある、などはコースの評価を下げる原因になっているとも言えます。
バンカー(Bunker)

筆者撮影
バンカーはゴルフコースの戦略性と景観に大きな影響を与える要素です。
良いバンカーを定義するには、まず位置、形状、数が求められます。
上級者のショット落下地点や次のショットが有利になる場所の近く、グリーン周りではアプローチライン上にバンカーを配置することで、ショットの質(=ショットバリュー)を問うデザインになります。
一方で初級者にとって避けようがない場所(例えばティーから短い距離のバンカーや、戦略上不利な位置に置かれたバンカー)はマッケンジーの挙げた理想とされる「弱いプレーヤーには常に迂回ルートが開かれていなければならない」に合致しておらず、フェアネスを欠きます。
バンカー配置の基本は、上級者にショットの質を問うべきものであり、初心者に罰を与えるものであってはならず、上級者には挑戦する喜びを、初心者には迂回する選択を提供すべきなのです。
次に形状と深さです。バンカーは造形要素としてコースの顔立ちを決めます。
リンクスコースではポットバンカーのように深く小さな丸いバンカーが多用され、これが海岸砂丘の風景と調和して“リンクスらしさ”を演出します。一方、米国東海岸のクラシックコースでは大ぶりで浅めのオーバル型バンカーが多く、白い砂との対比で美しい曲線美を描いています。
設計者はそのコースの地形や景観コンセプトに合ったバンカー形状を描きますが、プレー面では、深すぎるバンカーは特に初心者には絶望的なハザードになるため要注意です。
バンカーの深さやアゴの高さは、リスクや難易度の調整弁となります。
最後にバンカーの数はコンディションに影響します。
バンカーは窪地であるというその形状から、コース内で最も雨水が流れ込みやすいアイテムです。
数が多くなればなるほど、メンテナンスのコストが上がり、管理面では最も手間のかかるアイテムでもあります。
そのため設計段階で、バンカー面積を必要以上に増やしすぎない、土壌層から水が湧かない場所を選ぶ等の考慮しながら、豪雨でも湖のように水が溜まらない構造にすることが良いバンカーの条件です。
最後に忘れてはならないのがバンカーの景観への寄与です。
バンカーはコース景観上のアクセントでもあり、適切な配置はホールの見た目を引き締めます。
例えば、何も障害の無い平坦なホールは間延びして見えるものですが、フェアウェイの要所にバンカー群があるだけでプレーヤーの目は目標を捉えやすくなり、風景にアクセントとリズムが生まれます。
「バンカーはコースの彫刻」と言われる通り、評価の高いコースではバンカーの一つひとつにアートのような個性があり、それがコース全体のキャラクターとブランドの形成につながっています。
グリーン(Green)

筆者撮影
グリーンはホールの最終目的地であり、カップが切られるパッティングエリアです。
ゴルフコースの設計要素の中でも特に 「コースの心臓部」 と言われるほど重要な存在です。
良いグリーンには多くの要件がありますが、分類すると大きさ・形状、傾斜、周辺との関係 といった点が挙げられます。
まず大きさと形状ですが、グリーンのサイズは狙いの距離やショットの難易度に応じて適切に設定されるべきです。
近代ゴルフ建築では700平米程度が一般的なサイズですが、ロングアイアンを使った長いアプローチが想定される場合は受け入れ範囲を広く取るため800平米以上の大きめのグリーンにしたり、一方ショートアイアンやウェッジで正確に狙えるホールでは500平米以下に絞って命中精度を要求するといった具合です。
また形状も、単なる丸や四角ではなく、多彩な輪郭や奥行きを持たせて戦略性を高めます。
時にはグリーンを二段・三段と段差をつけて、高低差でピン位置ごとの難易度を変化させることもあります。グリーン形状の工夫は無限であり、設計者は地形を読みながらそのホールに相応しい形をデザインします。
傾斜(アンジュレーション)もグリーン設計の要です。
平坦なグリーンは易しく、強い傾斜のグリーンは難しいというのは直感的に分かりやすいですが、実際はその塩梅が最も難しい部分です。優れたグリーンは一見平穏に見えて、近づくと局所的な多面で構成されています。
これによりカップ位置によってホールの難易度が大きく変わり、プレーするたびに異なる挑戦を提供できるというわけです。
全体の傾斜が強すぎるとカップを切れるエリアが限定されてしまったり、トーナメントの高速化されたグリーンではボールが止まらないなどの弊害が出てきてしまうため、グリーン全体の中でカップが切れる程度の面(最低6-8箇所)を繋ぎながら、周囲のハザードや地形と連動させながら、適切な緩急をつけて勾配を設計することが求められます。
例えば13ft以上のグリーンスピードを出すと2.5度以上の勾配ではボールが止まらなくなるので、トップレベルの競技を想定するコースでは、グリーンは平な平面を大きな勾配で繋ぐ形状になります。
最後にグリーン周辺エリアとの関係です。
グリーン単体が良くても、その周囲(グリーンエプロンやマウンド、チッピングエリア等)のデザインが悪ければ真価を発揮しません。良いコースではグリーンを取り囲むエリアも含めて「グリーンコンプレックス」と言われます。
例えばグリーン手前のフェアウェイはグリーンと同程度の長さで刈り込み、転がしを誘発する設計にしたり、グリーン奥にはマウンドを設けてオーバーした球が戻ってくるようにするなど、周辺の造形と組み合わせることでグリーンの攻略に多様性を与えます。
グリーンはホールの終着点であると同時にデザインの集大成ともいえる場所であり、その完成度がコース全体の評価を左右するのです。
設備と機能(灌水や排水)が作り出す高品質の芝生
良いゴルフコースを語る上で忘れてはならないのが、コース管理(メンテナンス)の側面です。
特に芝生の生育に関わる灌水(かんすい:潅水、散水)設備と排水設備は、コースのプレー品質を根底から支える重要インフラです。
優れた設計を活かすも殺すも、この設備と機能次第と言っても過言ではありません。
排水(Drainage)

まず排水については、コース管理の世界で「ゴルフコースでもっとも大事な言葉は 排水、排水、排水」と半ばジョーク混じりに言われるほど重視されています。
地形的に水が溜まらない造形やルーティングをとること、必要に応じて排水溝や暗渠パイプを張り巡らせること、バンカー内やグリーン下にもしっかり排水管を入れることなど、設計・施工段階から排水計画は綿密に練られるべきです。
排水が良ければ雨天直後でもプレーが可能となり、コースクローズによる機会損失や、管理のコストが減り経営にもポジティブな影響を与えます。また、水はけの悪い場所では芝生病や地力低下も発生しやすく、結果的に施肥や施薬も増えて、環境的にも悪循環に陥ります。
したがって、良いコース=排水の良いコースと言って差し支えないほど、排水能力はゴルフ場において重要な要素です。
灌水(Irrigation)

筆者撮影
次に灌水(潅水)設備、つまりスプリンクラーによる散水システムです。
芝生は十分な水分がなければ育ちませんが、与えすぎれば病気になり、タイミングや量の精密なコントロールが要求されます。かつての手動スプリンクラーと違い、今や自動灌水システムはコンピュータ制御で極めて細かくエリアごとの水量調整が可能です。これにより均一で高品質なターフを維持できるようになりました。USGAも「良好なコースコンディションを維持する上で、灌水システムは疑いなく最も重要なツールの一つだ」と述べています。
特に夏場の乾燥期には、大量の水が必要とされ、これを安定して供給できる灌水設備がないと芝は弱ります。
また、高性能な灌水設備は単に芝を潤すだけでなく、水の節約や肥料・薬剤の散布効率化にも役立ちます。
センサーや天候連動型のシステムを導入すれば必要最低限の水だけを撒くことができ、結果的に環境負荷の低減にもつながります。近年はSDGsの観点からもゴルフ場の水資源管理は注目されており、スマート灌水システムへの投資は時代の要請ともいえます。
排水と灌水、この両輪がうまく機能して初めて、グリーン・フェアウェイの健康で美しい芝生が育ちます。
素晴らしい設計もコンディションが悪ければ台無しであると同様に、退屈で平凡な設計でもコンディションが抜群に良ければゴルファーの評価は上がるものです。
裏を返せば、大規模なデザインの変更をしなくとも、メンテナンスを支える設備と人こそがコースの価値を上げるとも言えますから、万全な排水・灌水の設備によって常に高品質な芝生を提供できるゴルフ場は、それだけで世界水準のコースと言えるでしょう。

コンセプトやプリンシパルの重要性

筆者撮影
以上、様々な観点から「良いゴルフコース」の要件を見てきましたが、最後に総括として強調したいのは、優れたコースには明確なコンセプト(理念)とそれを支える設計原則の一貫性があるという点です。
ゴルフコースも一つの作品であり、設計者の思想やテーマが全18ホールを貫いている場合、それはプレーヤーにも強く伝わります。
よく「コース全体がひとつの物語を語りかけてくる」「アルバムの曲が並ぶように統一感と起伏がある」と表現されますが、まさに名コースは各ホールが調和しつつもそれぞれの個性を放ち、ラウンド全体でひとつの芸術作品のような完成度を示します。
具体例として、アリスター・マッケンジーが1920年にまとめた13の設計原則に書かれた思想や理念は100年を経てもなお色褪せず、多くの名コースがこの原則を体現しています。
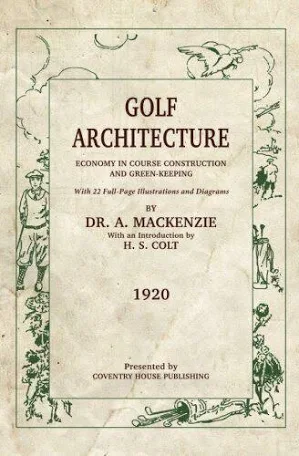
一方で、コンセプト不在で場当たり的に造られたコースは、ホールごとの関連性が乏しく散漫な印象になりがちです。
例えばデザインテーマが統一されていないと、「良いホールもあるが全体として見るとバラバラ」という評価になってしまいます。
ゴルフ評論家ジェフ・シャックルフォードは「音楽アルバムに例えれば、ベストコースはベストアルバムのように統一感と変化が同時に存在する」と述べています。まさにその通りで、18曲(=18ホール)が雑多に並ぶのではなく、一貫したテイストの中で緩急や盛り上がりがある構成が望ましいのです。
総じて、「良いゴルフコース」に共通するのは、確固たるデザインコンセプトを持ち、それに沿って全要素がデザインされていることです。加えて、そのコンセプトがクラシックな原則(戦略性・美観・フェアネス等)の上に成り立っていることも重要です。
設計者だけでなくコース運営者にとっても、自分たちのコースのコンセプトは何か、それはゴルフ建築の原則に沿っているかを見直すことが、コース改善やブランディングの指針となるでしょう。
まとめ
良いゴルフコースをデザイン・建築するための法則とルールについて、歴史的な視点から現代の理論まで概観しました。
名設計者たちが遺した教訓や、Tom Doak氏・Richard Mandell氏らによる現代のバイブル的知見を踏まえれば、結局のところ大切なのは 「すべてのプレーヤーにとって面白く、公平で、美しく、そしてメンテナンスの持続可能性を持ったコース」 を作ることだと言えます。
戦略性・美観・プレイアビリティという不変の価値を追求しつつ、最新技術や環境配慮も取り入れ、コンセプトを明確に持ったコースは時代を超えて支持されています。
ゴルフ場のオーナーや経営者にとって、コースそのものが最大の商品であり資産です。
その価値を高め維持するためには、設計・施工段階からメンテナンス、そして改修に至るまで一貫したビジョンが必要でしょう。本稿で述べたような原則を念頭に、皆様のゴルフ場が「良いゴルフコース」として末永く愛されることを願ってやみません。